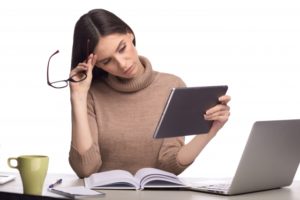適応障害という診断を受け、休職を余儀なくされた人々にとって、職場復帰は一筋縄ではいかない挑戦です。
しかし、適切なアプローチと段階を踏むことで、この挑戦を乗り越えることは可能です。
心身の健康を回復させることから始め、職場環境の改善、自己分析といったステップを経て、復帰へと進むことが大切です。
このプロセスを通じて、再発のリスクを最小限に抑えながら、より強く、柔軟な自己へと成長することができます。
本稿では、適応障害からの復職に向けた心構えと具体的なステップ、再発防止のための戦略について、わかりやすく解説していきます。
適応障害で休職中の人が復帰するためのステップ
適応障害で休職してしまった方は、復帰するためにどうすればいいのでしょうか?
適応障害とは、ストレスや環境の変化に対応できずに、不安や抑うつなどの症状が生じることをいいます。
適応障害で休職する方は、仕事に対するストレスが大きかったり、職場の人間関係に悩んでいたりすることが多い傾向にあります。
しかし、適応障害は治療すれば回復できる可能性が高いため、休職中に心身の健康を回復させることが最優先です。
心身の健康を回復させるためには、以下のステップを踏むことがおすすめです。
ステップ1:主治医への定期的な受診と服薬
適応障害は、主治医との定期的な受診と服薬が治療の基本です。主治医から処方された薬は、必ず指示通りに服用しましょう。
薬は、不安や抑うつなどの症状を和らげる効果があります。また、主治医や臨床心理士との面談では、自分の気持ちや悩みを話すことで、心理的なサポートにもなります。主治医と信頼関係を築くことが大切です。
ステップ2:自分に合ったリラックス法を見つける
休職中は、自分に合ったリラックス法を見つけて実践しましょう。リラックス法とは、自分の心と体をリラックスさせる方法です。
リラックス法には、呼吸法や瞑想法などの心理的な方法、マッサージやヨガなどの身体的な方法があります。
リラックス法を行うことで、ストレスホルモンの分泌を抑えたり、自律神経のバランスを整えたりすることができます。
リラックス法は、自分に合ったものを選ぶことが重要です。自分に合わないものを無理に行っても効果がありません。
ステップ3:日常生活のリズムを整える
休職中は、日常生活のリズムを整えることも大切です。日常生活のリズムとは、起床時間や就寝時間などの生活習慣です。
日常生活のリズムが乱れると、睡眠不足や食欲不振などの身体的な不調や、気分の落ち込みやイライラなどの精神的な不調が起こりやすくなります。
日常生活のリズムを整えるためには、以下のことに注意しましょう。
- 毎日決まった時間に起きて寝る
- 朝日を浴びて体内時計をリセットする
- 食事はバランスよく規則正しく摂る
- 適度な運動をする
- 昼寝は15分以内にする
ステップ4:環境に適応できないことの原因分析と対策
心身の健康が回復したら、次に環境に適応できないことの原因分析と対策を考えましょう。
環境に適応できないことの原因は、人それぞれ異なります。例えば、以下のようなものがあります。
- 仕事量や責任が多すぎる
- 仕事内容や方針に納得できない
- 職場の人間関係がうまくいかない
- 自分の能力や適性に合わない
- 自分の価値観や目標と合わない
原因分析を行うときは、自分ひとりで悩まずに、主治医やメンタルヘルス担当者、産業医などの専門家と相談しましょう。
専門家は、客観的な視点からアドバイスをくれたり、職場との交渉をサポートしてくれたりします。
原因分析ができたら、対策を考えましょう。対策には、以下のようなものがあります。
- 仕事量や責任を減らす
- 仕事内容や方針を変える
- 職場の人間関係を改善する
- 自分の能力や適性に合った仕事に変える
- 自分の価値観や目標を見直す
対策を考えるときは、自分が納得できるものを選びましょう。無理に復帰する必要はありません。
また、対策を実行するときは、主治医や専門家と相談しながら段階的に行いましょう。
適応障害で休職中の人が復帰するメリットとデメリット
適応障害で休職中の人が復帰することには、メリットとデメリットがあります。以下にそれぞれを示します。
復職するメリット
- 仕事によって得られる収入や社会的地位が保たれる
- 仕事によって得られる達成感や充実感が得られる
- 仕事仲間やお客様との交流が増える
- 自分の能力やスキルを発揮できる
- 自分の役割や目標が明確になる
復職したときのデメリット
- 仕事によって生じるストレスや負担が増える
- 仕事内容や方針に不満や不安が生じる
- 職場の人間関係にトラブルや摩擦が生じる
- 自分の能力や適性に合わない仕事に追われる
- 自分の価値観や目標と合わない仕事に疑問を感じる
適応障害で休職している人が復帰できると判断される目安
復職できるかどうかは主治医の判断がいちばんです。
ですが、少しずつ回復してきていて自分でもそろそろ復職に向けて心身の準備をしていきたいと感じているとき、復職のタイミングがいつなのかどうやって見極めたらよいのでしょうか。
適応障害で休職している人が復帰できると判断される目安は、大きく分けると、規則正しい生活ができているか、仕事に対する不安や抵抗感が減っているかの二つです。
それぞれポイントをお伝えします。
規則正しい生活ができているかをチェック
適応障害で休職した人が復帰できると判断される目安の一つは、規則正しい生活ができているかどうかです。
規則正しい生活ができているということは、心身のバランスが整っているということです。
昼夜逆転など規則正しい生活ができていないと、心身の不調が続き、再発や悪化のリスクが高まります。
産業医がいる事業場の場合は、産業医との面談が行われ、生活習慣や症状の状況などを報告し、復職に向けて、動いていくことになります。
仕事に対する不安や抵抗感が減っているかをチェック
適応障害で休職した人が復帰できると判断される目安のもう一つは、仕事に対する不安や抵抗感が減っているかどうかです。
適応障害は、仕事のストレスや人間関係などの原因によって発症する場合が多いです。そのため、仕事に戻ろうとすると、再びストレスを感じたり、嫌な気持ちになったりすることがあります。
仕事に対する不安や抵抗感が減っているかどうかは、自分自身で気づくこともあります。例えば、以下のようなことがあれば、仕事に対する不安や抵抗感が減っていると言えます。
- 仕事に関する話題に興味を持つ
- 仕事仲間や上司から連絡が来たら返信することが苦痛ではない
- 復職後の仕事の内容や環境について考える
適応障害で休職した人は、復帰に向けて焦らず、自分のペースで回復に努めましょう。
規則正しい生活を心がけて、仕事への不安や抵抗感を減らしていくことが大切です。復帰後も、仕事の負担や人間関係などに注意して、再発を防ぐようにしましょう。
適応障害で休職している人が復帰する前にしておきたいこと
適応障害で休職していた人が職場復帰できることになったとしても、いきなり前と同じような時間帯と業務内容で仕事をするのは難しいでしょう。
まず慣れるまでは、心身に負荷をかけないように働くようにしましょう。
会社の規定にもよりますが、時短勤務やノー残業など勤務時間を調整してもらったり、業務内容を軽くしてもらったりなどしてもらうといいでしょう。
職場復帰の前には人事課の方との面談があるものです。その場に職場の人も出席するでしょう。その場で、今後の仕事について相談しましょう。
もし、適応障害になった原因が職場環境にあるようであれば、配置換えしてもらうことも一つの手です。
自分が適応障害になった原因をしっかり分析して、復帰後に再発しないような環境づくりをしてもらうようにしましょう。
また、適応障害になる原因の一つとして「頑張りすぎてしまうこと」があげられます。そのため、少しでも疲れたら休憩することも大事です。
復帰後はとにかく負荷をかけず、無理せず働くようにしましょう。
適応障害での休職からの復帰には慎重な行動が必要
職場復帰間際になると、通院している主治医の先生から「復帰できそうだ」と言われます。ただ、この時に焦らないようにしましょう。
休職していることで同じ部署の人達に迷惑をかけているからと、早く復帰しようと考える人がいるものです。
しかし、適応障害になった原因が解決できていないのであれば、復帰しても再発してしまう可能性があります。
主治医の先生は会社の環境のことはよくわかりません。適応障害になった原因が職場環境にあるようであれば、まずはその原因を解決する必要があります。
そのため、主治医の先生から復帰できそうなことを言われたとしても慎重に行動するようにしましょう。
原因が会社の職場環境にあるのであれば、その環境を改善してもらうことが必要です。復職前には人事との面談もある場合が多いので、環境に問題がある場合にはその場で相談してみましょう。
適応障害での休職から復帰する場合は、再発させないためにも、今後のことをしっかり考えながら慎重に進めていくようにしましょう。
適応障害での休職から復帰した後、再発させないためには
適応障害で休職した原因が職場環境にあるのであれば、同じ職場に復帰したとしても相当なストレスがたまり、病気が再発して再び休職ということになりかねません。
ですので、職場環境に原因がある場合には、異動させてもらうなどして環境を改善してもらうことがベストでしょう。
ただ、異動させてもらったとしても、新しい環境も適応障害を発症した場合は自己評価が低くなってしまいます。また、周囲からの評価も低くなり、最悪の場合、退職せざるをえなくなるかもしれません。
ですから、休職中にしっかり自分を見つめ直すことも重要です。適応障害になった原因にはその環境に適応できていないことがあります。
適応できていないのはものごとの捉え方や考え方に原因があることが多いものです。
ですから、適応力を高めるためには、ものごとの捉え方や考え方を柔軟にしていく必要があります。精神科では、精神療法によって柔軟にするための訓練があります。
また、みんなそれぞれものごとの捉え方や考え方が異なるということを受け入れることも大事です。
このように適当障害を再発させないためには、環境を改善することも大事ですが、自分を見つめ直すことを必要となってきます。
まとめ
適応障害からの復職は、自己の心身の回復を最優先にしながら、職場環境の改善や自己分析を通じて、再発のリスクを減らすことが重要です。
この過程で、主治医や専門家との連携、職場とのコミュニケーションが不可欠となります。
また、復職後も自己の限界を理解し、無理をせず、適切な休息を取ることが再発防止につながります。
本稿では、適応障害による休職からの健全な復職への道のりを、具体的なステップと共に紹介しました。
この情報が、同じような状況にある人々の支援となり、一人でも多くの人が健康的な職場復帰を果たせることを願っています。